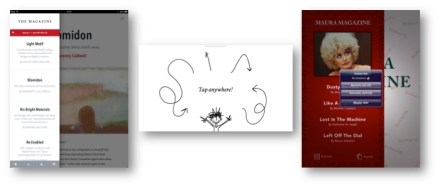モバイル・動画・ペイウォール・広告——。
日本のデジタル報道メディアの試みを大きくリードする米国の新聞電子版の動き。
Wall Street Journal を中心としたデジタルネットワークを統括する経営幹部が考える、デジタルメディア戦略、焦眉の課題を紹介する。
日本経済新聞、朝日新聞を筆頭に、日本でも新聞各社が電子版(Web やモバイルアプリ)への取り組みピッチを上げています。ただし、惜しいことに“新聞の未来”へと向かう戦略の子細やリアリティが、いまひとつ伝わりません。
一方、米英の新聞メディアでは、電子版を推進するリーダー格がその目指すところを具体的に語るケースが多く、新聞メディアビジネスに直接関わらない筆者も参考にしています。
本ブログでは、過去に New York Times (NYT)電子版に功績のあった Jim Roberts 氏(同氏は2013年に NYT を辞職、現在は Reuters digital の Executive Editor に就任している)のオピニオンを紹介しました(「モバイル、ソーシャル、ペイウォール New York Times その取り組みを語る」)。本稿では、電子版有料化の老舗であり、そして動画サイトをはじめ数々の実験的な試みを行ってきた Wall Street Journal(WSJ)のキーパーソン Raju Narisetti 氏のオピニオンを紹介します。
同氏は、記者・編集者としての長いキャリアを WSJ で送り、2009年から Washington Post 編集部門の最高責任者のひとりとして、特にデジタルメディアビジネス(Web サイト、モバイルおよびタブレット)で采配を振るいました。その後、2013年に WSJ を傘下に擁する親会社、新 News Corp(旧 News Corp がスキャンダルや業績不振の影響で分社して誕生したメディア企業の統括親会社)の戦略担当 SVP に就任しました。
WSJ は、最近話題の NYT の電子版有料化(ペイウォール)に先行しており、その有料購読者100万人級の実績を誇っています(参考 → これ)。
Nieman Journalism Lab 掲載のインタビュー記事「Monday Q&A: Raju Narisetti on designing for mobile, the paywall fallacy, and reinventing ads」(「Raju Narisetti が語る:モバイル設計、誤ったペイウォール、そして広告の再発明」)で、同氏はソーシャルメディアへの自身の関わり、ジャーナリズムとビジネスの両立、モバイルや動画への取り組み、さらにペイウォールに関する誤った認識や広告ビジネスの再構築など、いずれもデジタルメディアが直面する広範でアクチュアルなテーマについて言及します。

Monday Q&A: Raju Narisetti on designing for mobile, the paywall fallacy, and reinventing ads » Nieman Journalism Lab via kwout
本稿は、そのロングインタビューから、モバイルと広告に関連する特筆すべき箇所を紹介します。インタビューの全体や表現の正確性については、ぜひ出典元記事を確認して下さい。
モバイルがもたらす変化と可能性を実践する
Narisetti 氏は、WSJ を統括し数々のデジタルメディアネットワークを統括する立場から、自社を取り巻く競争環境に言及しますが、その重要な対象は“競合他社”ではないとします。
私が堅く信じているのは、われわれは競合について考えるのを止めるべきだということです。それは New York Times、Gurdian、FT、あるいは Bloomburg、Reuters といったものです。というのも、今日の読者はとても雑食的だからです。それはテクノロジーがもたらしたものです。
われわれが本当に競合しているものとは、読者にとって唯一再生不能なもの、つまり彼らの時間(の獲得競争)です。もし、それを5分でも、10分でも、そして15分以上でも獲得できるのなら、競合を気にする必要はありません。読者がどこでその時間を使っていようが勝つことができます。
モバイルは同氏が語るように、読者がメディアに振り向ける可処分時間を拡大するためには、非常に重要な戦略分野です。
一方、そこへのメディア事業のリーダーらの認識が十分でないと指摘します。
(モバイル化で)生じている本格的な変動は、記者や編集者にとってだけではありません。メディア事業のリーダーがいまだ認識していないと私は考えます。
Web においては、ビジネスモデルにおける変化がわれわれの気の付かないまま起きてしまいました。同じような過ちをモバイルにおいて犯したくありません。読者の動向、いかにマネタイズするか、各デバイス向けにいかに訴求力のある広告を創造するかなどについて、新聞社のリーダー層は、これについて語り、資源をもっと注ぐことができるはずです。……おそらく世界中の新聞メディアで編成されているモバイル向けのチームは、いずれも一ケタのスタッフ、たまたまでも10名程度に過ぎないでしょう。この現状を心配しています。
一方、タブレットとスマートフォンという潮流の分岐にともなうメディアの適合方法について問われ、Narisetti 氏はより子細なビジョンを示します。
タブレット対スマートフォンにおいては、明瞭に異なった考えを持つべき理由があります。デバイスの寸法、機能性、そしてそれが表示できるものに違いがあるからです。タブレットには自由度と柔軟性があります。課題はタテ・ヨコそれぞれの表示にコンテンツをシームレスに適合させるテンプレートを豊富に用意することです。
一方、本当の課題や闘いは、スマートフォンにあります。コンテンツ消費パワーの最大の源はここにあります。
Washington Post 時代の例をあげましょう。そこで9.11以後における政府契約における腐敗を追及したすばらしい調査報道の企画がありました。それは、話題を呼び印刷版で読者の強い支持を得ました。その理由は、とても入念に、印刷版とPC サイト用に準備したものだったからです。長い記事であるために、デザイナーは記事への動線としてリード文を配置しました。
しかし、われわれは、モバイル向けのコンテンツというものをすっかり失念していました。私の勘定したところでは、BlackBerry 上で記事を読み終えるのに46ページも要したのです。だれも読みはしません。記事冒頭のリード文でさえ、モバイルでは7ページも要したのです。私が伝えたい教訓は、「われわれはこんな企画は止めるべきだ」ではありません。次に、このような大きな調査報道記事をモバイル読者に提供する際には、最初のページに簡潔な要約を設け、記事が長大なものであることを断り、PC サイトや印刷版で読むことを勧めるか、モバイルでの閲読にこだわる読者のために、記事の各箇所への多くのリンクを提供すべきだということです。
重要なことは、モバイルにおけるコンテンツ体験が(他に対し)著しく異なっていることであり、それを知り、それにいかにアプローチするかをスタッフに伝えなければなりません。
広告のイノベーション、メディア自らが立ち向かうべきとき
Narisetti 氏は、また、メディアビジネスの焦眉の課題、広告ビジネスの革新についても述べます。
同氏は、WSJ のような、デジタルメディアの運営者は提供する多様なコンテンツについて、来訪読者によるページビューやランキングなどの多くを知っていると述べます。ところが、同時にこれらコンテンツとともに掲載される広告に、読者がどうかかわっているかほとんど知らない点を指摘します。
われわれは広告に関する読者の動きのほんのわずかしか知りません。それは、 (広告サーバー ASP 事業者の)DoubleClick やアドネットワークの類、そして(広告レコメンドサービスの)Outbrain らに対して読者を割譲してしまっているからです。
「私たちは、読者がどう広告と関係しているかあなたが知るのを手伝います」「もっとうまくマネタイズするのを手伝いましょう」と彼らはいいます。“それはすばらしい!”と使い始めました。しかし、われわれは自ら読者との関係を築き、メディアの上で読者が広告とどう関わっているかを知らなければならないと、私は徐々に考えるようになってきました。それがより良いマネタイズのためのスイートスポットとなるのです。われわれはこういった情報を得ることを放棄し、他社へ割譲してきました。これを取り戻す必要があります。メディアにおける広告イノベーションの多くは、“(読者の行動を)邪魔する広告”です。だれかがやってきて“これをおたくの読者の面前で爆発させていいいですか?”と問えば、“いいえ、結構です”というべきなのです。それは読者にとり良い体験ではない。それは結果的に収入減をもたらすと。
私がいいたいのはこうです。広告イノベーションも、メディアのイノベーション同様に、われわれの事業のミッションのひとつとして遂行すべきだということです。広告におけるイノベーションを第三者へと割譲すべきでありません。そこに参加し、創造すべきです。われわれはそれを本の少し、不十分にしか行っていません。
広告主やマーケターがますますコンテンツ創造の分野に入り込んでいるのに、怠慢にも座していてはいけません。“われわれのメディアでリーチしている読者に届ける革新的な広告を創造し、広告主に対して何を手助けできるか”と自らに問うべきなのです。
モバイルと広告という二つのアクチャルなテーマについて、実践に裏打ちされた豊かな見識を紹介するだけで、分量が尽きてしまいました。
ちなみに、「もっとも関心を持っている技術分野は何か」との問いに答えて、Narisetti 氏は「Android のことでは夜も寝られない」と述べています。
Android デバイスでは、われわれはユーザー体験上も、支払いモデルについてもうまくできていません。iOS デバイスでは、読者は支払う意思を示すため、自然とそこにわれわれは引き寄せられてきました。しかし、Android の成長は、特に米国外で大きいものがあります。したがって、われわれは、Android でのより良い体験とマネタイズ(手法)を提供しなければなりません。
次の機会には、本稿で紹介できなかった動画コンテンツビジネスの革新性などに触れた箇所を紹介したいと思います。
(藤村)